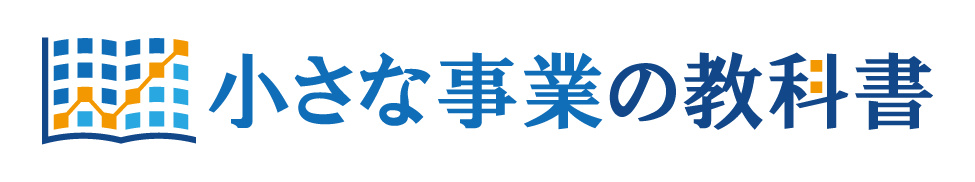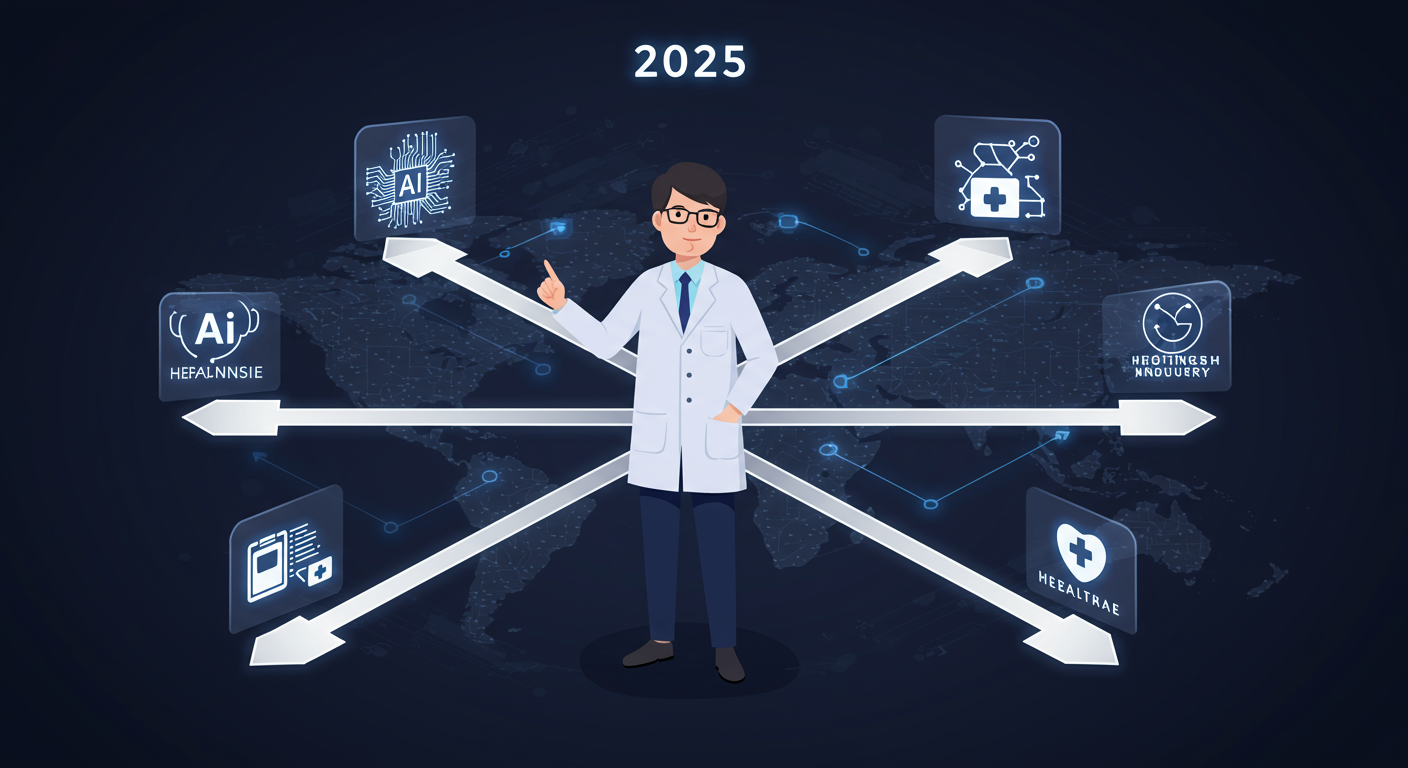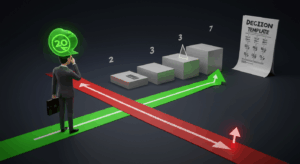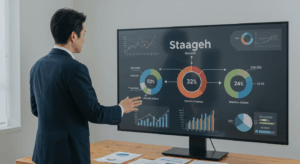起業で成功するためには、これから伸びる業界を見極めることが重要であり、事業の成否はその選定に大きく左右されます。
この記事では「これから伸びる業界で起業」をテーマに、AI、クラウドサービス、フィンテック、ヘルスケア、再生可能エネルギー、オンライン教育の5分野を取り上げています。
それぞれについて、成長要因や短期〜中期の見通し、参入の難易度、代表的な事業モデル、初期投資の目安をシンプルに比較し解説します。
 相談者
相談者限られた時間で成長性と参入リスクを比較して候補を3〜5業界に絞りたいです。



人工知能やフィンテック、ヘルスケア、再生可能エネルギー、オンライン教育を成長要因・短中期見通し・参入難易度・初期投資で短く比較します。
- 5業界の成長を支える要因の比較
- 短期〜中期の市場見通しまとめ
- 参入難易度と初期投資感覚の提示
- 代表的事業モデルと規制上の注意点
2025年に起業を成功させるための業界選定の3つの視点
2025年に起業を成功させるためには、社会の変化を的確に捉え、成長市場を見極める視点が何よりも重要です。
闇雲に事業を始めるのではなく、テクノロジーの進化と社会課題の変化、政府の支援策と市場の将来性、自身のスキルを活かせる分野の見極めという3つの視点から総合的に判断しましょう。
これらの視点を組み合わせることで、失敗のリスクを最小限に抑え、持続可能な事業を構築するための土台を築くことができます。
テクノロジーの進化と社会課題の変化
テクノロジーの進化と社会課題の変化は、新たなビジネスチャンスを生み出す大きな原動力となります。
特に、日本の少子高齢化や労働人口の減少といった課題は、テクノロジーによる解決が強く求められています。
実際に、経済産業省の試算では2030年に最大で約79万人のIT人材が不足すると予測されており、業務のデジタル化や自動化に対する需要はますます高まっていきます。



技術や社会の変化って、どうやってビジネスチャンスに結びつければいいの?



社会が抱える「不便」や「問題」を、最新技術でどう解決できるか考えてみましょう。そこに大きなヒントがあります。
| テクノロジー | 関連する社会課題 | ビジネスチャンスの例 |
|---|---|---|
| 人工知能(AI) | 労働人口の減少、生産性向上 | 業務のデジタル化、マーケティング自動化 |
| IoT | 高齢者の見守り、遠隔医療の必要性 | オンライン診療、介護テック |
| ブロックチェーン | 取引の透明性、データセキュリティ | フィンテック、サプライチェーン管理 |
このように、社会の変化に常にアンテナを張り、課題解決に貢献できる技術の活用法を考えることが、これから伸びる業界で起業するための重要な第一歩です。
政府の支援策と市場の将来性
国がどの分野に投資し、成長を後押ししているかを把握することは、事業の追い風を知るうえで欠かせません。
政府の支援策や法規制の動きは、市場の将来性を示す重要な指標となります。
例えば、日本政府が掲げる「GX(グリーン・トランスフォーメーション)」の実現に向けては、今後10年間で150兆円を超える官民投資が予定されています。
これにより、再生可能エネルギーやカーボンニュートラル関連分野で起業する大きなチャンスが広がっています。
| 政策・支援策 | 対象となる主な業界 | 具体的な事業例 |
|---|---|---|
| DX推進政策 | 人工知能(AI)、クラウドサービス | 中小企業の業務効率化SaaS提供 |
| GXリーグ基本構想 | 再生可能エネルギー、環境技術 | カーボンニュートラル支援コンサルティング |
| スタートアップ育成5か年計画 | 全般(特にディープテック) | 大学発ベンチャーへの投資・育成支援 |
経済産業省や中小企業庁が発表する資料や補助金情報を定期的に確認し、国の支援がある成長市場を見極めることで、起業時の資金調達リスクを抑えることができます。
自身のスキルを活かせる分野の見極め
業界の成長性という外的な要因だけでなく、自身の強みや経験を活かせるかという内的な要因も、事業を長く継続させる上で非常に重要になります。
どれほど有望な市場であっても、自分が価値を提供できなければ成功するのは難しいものです。
これまでのキャリアで培ってきた専門知識や人脈は、起業における他社にはない強力な武器となります。



自分のスキルがどの業界で通用するかわからない…



まずはご自身の経歴を棚卸しして、得意なことや情熱を注げることをリストアップしてみましょう。それが業界選びのヒントになります。
| 保有スキル・経験 | 親和性の高い業界 | 事業アイデアの例 |
|---|---|---|
| ITエンジニアリング | 人工知能(AI)、フィンテック | 特定業界向けAIモデル開発、決済API提供 |
| 営業・マーケティング | オンライン教育、SaaS | 集客に特化したオンライン講座、マーケティング自動化ツール |
| 医療・介護職 | ヘルスケア、介護テック | 現場目線のオンライン診療システム開発支援 |
これから伸びる業界の中から、自分のスキルや情熱を最大限に発揮できる分野を選ぶことで、競合との差別化が可能になり、持続的な事業モデルを築くことができます。
【2025年版】これから伸びる業界で起業するための有望5選の徹底比較
2025年にこれから伸びる業界で起業を成功させるためには、どの市場で戦うかという業界選びが最も重要です。
市場の成長性を正しく捉えることで、事業の成功確率を大きく高めることができます。
ここでは有望な5つの業界として、人工知能(AI)、フィンテック、ヘルスケア、再生可能エネルギー、オンライン教育を取り上げ、それぞれの特徴を比較していきます。
| 業界 | 成長を支える要因 | 参入難易度 | 初期投資の目安 |
|---|---|---|---|
| 人工知能(AI) | データ需要増、政府のDX推進 | 中〜高 | 300万円〜3,000万円 |
| フィンテック | キャッシュレス普及、政府支援 | 中 | 500万円〜5,000万円 |
| ヘルスケア | 高齢化、オンライン診療の需要増 | 中 | 200万円〜2,000万円 |
| 再生可能エネルギー | 政府目標、企業のESG投資 | 中〜高 | 100万円〜1億円 |
| オンライン教育 | リスキリング需要、人材育成投資 | 低〜中 | 50万円〜1,000万円 |
この比較から、あなたのスキルや自己資金に合った業界を見極めることが、成功への第一歩です。
人工知能(AI)分野:業務のデジタル化を推進する事業モデル
人工知能(AI)とは、人間の脳が行うような学習や判断をコンピュータで再現する技術のことです。
データの活用がビジネスの競争力を左右する現代において、AIによる業務のデジタル化はあらゆる産業で求められています。
特に、AWSやGoogle Cloudといったクラウドサービスの普及により、中小企業でもAI技術を導入しやすくなったことで、市場は今後3年から7年で爆発的に拡大すると予測されています。



AI業界って、専門知識がないと起業は難しいですか?



必ずしもそうではありません。業務自動化SaaSのように、特定の課題を解決するサービスならチャンスは十分にあります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 成長を支える要因 | データ需要増、クラウドサービスでの処理容易化、政府のDX推進 |
| 短期〜中期見通し | 1〜3年でBtoB自動化需要拡大、3〜7年で産業横断的導入 |
| 参入難易度 | 中〜高(技術人材の確保が鍵) |
| 代表的な事業例 | 業務自動化SaaS、画像解析サービス(Preferred Networks、ソニー) |
| 初期投資の目安 | 300万円〜3,000万円 |
| 注意点 | 個人情報保護法への対応、ソフトバンクやNTTデータなど大手との競合 |
この分野で起業する際は、技術人材の確保が大きな課題となります。
しかし、ニッチな領域に特化することで、大企業と競合せずに独自のポジションを築くことが可能です。
フィンテック分野:電子決済の普及で拡大する市場
フィンテック(FinTech)とは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、IT技術を活用した新しい金融サービス全般を指します。
政府のキャッシュレス推進策を背景に、PayPayや楽天ペイなどの電子決済サービスが急速に普及しました。
この流れは今後、個人間だけでなく企業間取引(B2B決済)にも広がり、市場はさらなる成長が見込まれます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 成長を支える要因 | キャッシュレス普及、政府支援、スマートフォン決済の利便性向上 |
| 短期〜中期見通し | 1〜3年でニッチ決済・B2B決済の伸長、3〜7年で金融インフラ統合 |
| 参入難易度 | 中(決済系の事業は認可と信頼構築が必要) |
| 代表的な事業例 | サブスクリプション向け決済プラットフォーム、電子決済API提供 |
| 初期投資の目安 | 500万円〜5,000万円 |
| 注意点 | 金融規制の遵守、楽天や三井住友カードなど大手との競合 |
決済関連の事業を始めるには金融庁の認可が必要となるため、参入のハードルは決して低くありません。
一方で、サブスクリプションモデルに特化した決済プラットフォームのように、特定のニーズに応えることで大きなビジネスチャンスが生まれます。
ヘルスケア分野:オンライン診療と介護テックの需要
ヘルスケア分野における介護テックとは、IT技術を用いて介護サービスの質や効率を高める製品やサービスのことです。
日本の深刻な高齢化を背景に、医療や介護の現場では人手不足が大きな課題となっています。
その解決策として、オンライン診療や介護ロボット、見守りシステムといったテクノロジーの活用に大きな期待が寄せられています。



医療や介護は規制が厳しそうなイメージですが…



その通りです。だからこそ、医療法規を深く理解した事業計画が成功の鍵になります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 成長を支える要因 | 高齢化、医療の遠隔化技術の進展、保険適用拡大 |
| 短期〜中期見通し | 短期でオンライン診療利用増、中期で介護ロボットや予防サービス拡大 |
| 参入難易度 | 中(医療法規・薬事法への対応が必要) |
| 代表的な事業例 | オンライン診療プラットフォーム(メドレー)、介護用ロボット導入支援 |
| 初期投資の目安 | 200万円〜2,000万円 |
| 注意点 | 医療法規の遵守、医師とのネットワーク構築が鍵 |
オンライン診療プラットフォームで成功したメドレーの事例が示すように、医師や医療機関との連携体制をどう築くかが、事業成長の大きな鍵となります。
再生可能エネルギー分野:カーボンニュートラル支援という可能性
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引いてゼロにすることを目指す国際的な目標です。
日本政府も2050年までの達成を掲げており、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)投資が活発化しています。
太陽光パネルや蓄電池のコスト低下も追い風となり、企業のカーボンニュートラル支援事業には大きな可能性があります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 成長を支える要因 | 政府目標の設定、企業のESG投資拡大、技術コストの低下 |
| 短期〜中期見通し | 3年以内に導入加速、中期で関連サービス拡大 |
| 参入難易度 | 中〜高(設備投資と法規制への対応が必要) |
| 代表的な事業例 | 住宅向け太陽光+蓄電池サービス、企業のカーボン削減コンサルティング |
| 初期投資の目安 | 100万円〜1億円(事業形態による) |
| 注意点 | 電力系統に関する規制、補助金の活用が重要 |
事業によっては高額な設備投資が必要ですが、国や自治体の補助金を活用することで初期コストを抑えられます。
また、企業の環境対策を支援するコンサルティング事業も有望な選択肢です。
オンライン教育分野:サブスクリプションモデルによる人材育成
オンライン教育におけるサブスクリプションモデルとは、月額などの定額料金で期間中に講座を自由に受講できるサービス形態です。
人生100年時代と言われる中で、社会人が専門スキルを学び直す「リスキリング」の需要が高まっています。
企業も人材育成への投資を増やしており、Udemy Japanのようなプラットフォームが人気を集めています。



質の高い教育コンテンツを作るのが大変そう…



優れた講師と提携したり、企業研修のニーズに特化したりすることで、競合との差別化が図れますよ。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 成長を支える要因 | オンライン学習需要の拡大、企業の人材育成投資、サブスクリプションモデルとの適合性 |
| 短期〜中期見通し | 短期でB2C・副業学習市場が拡大、3〜5年で企業研修領域へ浸透 |
| 参入難易度 | 低〜中(コンテンツの作成力とマーケティングが鍵) |
| 代表的な事業例 | 専門スキル講座のサブスクリプションサービス、企業向けLMS導入支援 |
| 初期投資の目安 | 50万円〜1,000万円 |
| 注意点 | コンテンツの品質競争、著作権への配慮 |
他の業界に比べて少ない初期投資で始められる点が大きな魅力です。
ただし、市場の競争は激化しており、成功するためには質の高いコンテンツと効果的なマーケティング戦略が欠かせません。
5業界の市場規模と成長率の比較
紹介した5つの業界について、市場規模と将来の成長性を比較します。
特に人工知能(AI)とフィンテックは、既存の産業構造を大きく変えるポテンシャルを秘めており、市場規模の拡大が最も期待される分野です。
| 業界 | 現在の市場規模(イメージ) | 将来の成長性ポテンシャル |
|---|---|---|
| 人工知能(AI) | 大 | 非常に高い(全産業への波及効果) |
| フィンテック | 中 | 高い(キャッシュレス社会の進展) |
| ヘルスケア | 大 | 高い(高齢化社会での必須サービス) |
| 再生可能エネルギー | 中 | 非常に高い(国策としての推進力) |
| オンライン教育 | 小〜中 | 高い(リスキリング需要の拡大) |
一方、ヘルスケアや再生可能エネルギーは社会的な需要が高く、国の支援も追い風となるため、安定した成長が期待できます。
オンライン教育は、個人の学び直しという大きな流れを捉えることで、急成長が見込める分野と言えるでしょう。
参入難易度と初期投資額の比較
起業を具体的に検討する上で、参入難易度と初期投資額は最も重要な判断基準のひとつです。
自身のスキルセットや用意できる自己資金と照らし合わせ、現実的な選択肢を絞り込みましょう。
| 業界 | 参入難易度 | 初期投資の目安 |
|---|---|---|
| 人工知能(AI) | 中〜高 | 300万円〜3,000万円 |
| フィンテック | 中 | 500万円〜5,000万円 |
| ヘルスケア | 中 | 200万円〜2,000万円 |
| 再生可能エネルギー | 中〜高 | 100万円〜1億円 |
| オンライン教育 | 低〜中 | 50万円〜1,000万円 |
オンライン教育は最も少ない資金で挑戦できる一方、再生可能エネルギーやフィンテックは専門知識と多額の資金が必要です。
人工知能(AI)やヘルスケアは、その中間に位置する分野と考えることができます。
有望業界での起業を実現する事業計画の具体的な立て方
有望な業界を見つけた後に起業の成否を分けるのは、精度の高い事業計画書を作成できるかどうかです。
アイデアを具体的な行動計画に落とし込むことで、成功の確率を大きく高められます。
これから解説する事業分野の絞り込みから、マーケットリサーチや競合分析、資金調達計画、さらに成功事例から学ぶ事業モデルの構築まで、順を追って進めていきましょう。
こうしたプロセスを丁寧に実行することで、事業のリスクを抑えつつ、持続的な成長の基盤を築けます。
3〜5つの候補から事業分野を絞り込む方法
有望な業界の中から、実際に取り組む事業分野を絞り込む際は、客観的な評価軸で点数化することが重要です。
情熱だけで判断せず、複数の視点から冷静に分析することで、最も成功確率の高い分野を見極められます。



たくさんの選択肢があって、どうやって絞り込んだらいいかわからない…



まずは評価軸を設けて、各候補を点数化する方法がおすすめです。
例えば、以下の表のように「市場の成長性」「収益性」「自身の強みとの合致度」「初期投資額」の4つの軸で各候補を5点満点で評価し、合計点で優先順位をつけます。
| 評価軸 | AI関連事業 | ヘルスケア事業 | オンライン教育事業 |
|---|---|---|---|
| 市場の成長性 | 5 | 4 | 4 |
| 収益性 | 4 | 3 | 4 |
| 自身の強みとの合致度 | 4 | 2 | 5 |
| 初期投資額(少ないほど高評価) | 2 | 3 | 5 |
| 合計点 | 15 | 12 | 18 |
この評価を行うことで、漠然とした候補の中から、自分に最も適し、なおかつ勝算のある事業分野を論理的に選び出せるようになります。
マーケットリサーチと競合分析の進め方
事業分野の候補を絞り込んだ後は、市場の需要を正確に把握するためのマーケットリサーチと、競合の強みや弱みを見極める競合分析を進めていきます。
データに基づいた客観的な事実を集めることが、事業戦略の精度を高める鍵となります。



市場調査って、具体的に何から始めればいいの?



まずは政府が公開している統計データで市場規模を把握し、次に競合企業のWebサイトやプレスリリースを確認しましょう。
マーケットリサーチと競合分析は、以下の手法を組み合わせて進めるのが効果的です。
特に、無料で利用できる情報源も多いため、積極的に活用して事業計画の根拠を固めていきます。
| 調査項目 | 具体的な手法 | 主な情報源 |
|---|---|---|
| 市場規模・成長率 | 定量調査 | 政府統計ポータルサイト「e-Stat」、業界団体のレポート、調査会社の公開データ(矢野経済研究所など) |
| 顧客ニーズ | 定性調査 | SNSでのキーワード検索、Q&Aサイト(Yahoo!知恵袋など)の悩み分析、想定顧客へのインタビュー |
| 競合の戦略 | 競合分析 | 競合企業のWebサイト、プレスリリース、決算資料、商品・サービスのレビューサイト |
| 業界の動向 | 情報収集 | 業界専門ニュースサイト、新聞社のWebサイト(日本経済新聞など) |
これらの調査から得られた情報をもとに、市場に存在する未解決の課題や、競合が見落としているチャンスを発見し、自社の事業が成功する独自のポジションを見つけ出します。
資金調達計画と活用可能な補助金の調査
事業を始めるためには、運転資金や設備投資のための資金調達が不可欠です。
自己資金だけで不足する場合は、融資や補助金・助成金の活用を視野に入れた綿密な計画を立てる必要があります。



自己資金だけだと不安…他にどんな資金調達の方法がある?



日本政策金融公庫の創業融資や、国・地方自治体が実施する補助金・助成金を活用するのが一般的です。
これから起業する方が利用しやすい資金調達方法には、それぞれ特徴があります。
事業の規模や性質に合わせて、最適な方法を組み合わせることが大切です。
特に、返済不要の補助金・助成金は積極的に情報を収集しましょう。
| 資金調達方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 日本政策金融公庫の融資 | 低金利で審査に通りやすい、実績がなくても借りやすい | 審査に時間がかかる場合がある、事業計画書の提出が必須 |
| 制度融資(自治体・金融機関・保証協会) | 自治体による利子補給などで金利負担が軽い | 手続きが複雑で、融資実行までに時間がかかる |
| 補助金・助成金(国・自治体) | 原則として返済が不要 | 公募期間が限定的、後払いのため一時的な自己資金が必要 |
| ベンチャーキャピタルからの出資 | 大規模な資金調達が可能、経営支援を受けられる | 経営の自由度が下がる可能性がある、株式の放出が必要 |
資金調達を成功させるためには、資金の必要性、その使い道、返済方法を具体的に示した事業計画書が重要な役割を担います。
成功事例から学ぶ持続可能な事業モデルの構築
最後に、安定して収益を生み出し成長を続けられる「持続可能な事業モデル」を構築します。
ゼロから考えるのではなく、同じ業界の成功事例を分析し、その要点を自社の戦略に取り入れることが成功への近道となります。



成功している会社は、何が違うんだろう?



顧客が抱える深い課題を解決し続ける仕組みと、市場の変化に柔軟に対応できる組織力を持っている点です。
例えば、有望業界で成功している企業は、それぞれ独自の強みとなる事業モデルを確立しています。
自社の事業に近いモデルを参考にし、どのように収益を上げ、顧客との関係を築いているのかを分析します。
| 企業名 | 業界 | 事業モデルの成功要因 |
|---|---|---|
| 株式会社メドレー | ヘルスケア | オンライン診療・求人情報など複数のサービスで医療業界の課題を多角的に解決、医師や医療機関との強力なネットワークを構築 |
| Preferred Networks | 人工知能(AI) | 深層学習の分野で世界トップクラスの技術力を保持、大手企業との共同研究開発による安定した収益基盤 |
| 株式会社ユーキャン | オンライン教育 | 長年の通信教育で培った教材開発ノウハウとブランド力、多様な資格講座を揃え幅広い学習ニーズに対応 |
これらの成功事例から、自社に応用できる収益化の方法や顧客獲得の戦略を学び取ります。
他社の成功パターンをただ真似るのではなく、独自の付加価値を加えることで、競争力のある持続可能な事業モデルを築くことができます。
まとめ
この記事では、人工知能(AI)、フィンテック、ヘルスケア、再生可能エネルギー、オンライン教育といった有望な5つの業界を比較しました。
特に、どの業界を選ぶかという業界選定が事業の成功を大きく左右します。
- 成長要因と短期〜中期の見通し
- 参入難易度と初期投資の目安
- 規制と補助金・資金調達の影響
- 自身のスキルとの親和性による候補絞り込み
まずは自己資金と持っているスキルを整理し、e-Statや業界レポートで市場規模や成長性を確認します。
そのうえで、補助金や規制の影響を確認し、候補を3つに絞って事業計画書を作成しましょう。