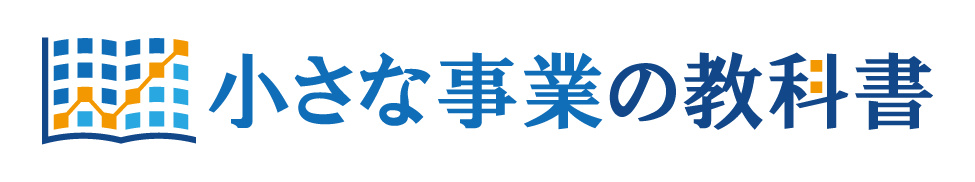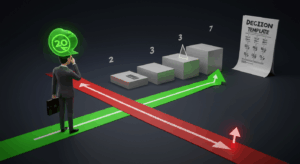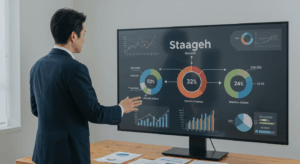新規事業開発がしんどい、つらいと感じるときに大切なのは、まず目の前の負荷を和らげて、勝ち筋を見極めることに集中することです。
本記事「新規事業開発がしんどい原因4つと今すぐできる5つの対処法」では、期待値のズレ、人手や予算の不足、意思決定の遅さといった主な原因を整理します。
加えて、1〜2週間で実行できる短期対処(優先タスクの明確化、MVPの定義、外部リソース活用基準の設定、心理的安全の確保)を紹介します。
さらに、中長期の視点ではロードマップのシンプル化やKPIの再設計、組織体制の見直しといった新規事業開発の進め方を、テンプレート付きで解説していきます。
 相談者
相談者立ち上げで成果が出ず、チームの士気が下がっているとき、まず何をすれば負荷を下げられますか?



まずは全タスクを可視化して上位5つに絞り、MVPを1機能×1顧客層で定義して週次で仮説検証を回します。
- 期待値のズレ・リソース不足・意思決定遅延の整理
- 1〜2週間で実行できる短期対処の手順
- 四半期単位でのロードマップとKPI再設計
- すぐ使える優先タスク・報告テンプレとメンタルケア施策
新規事業開発の「しんどい」を乗り越える短期対処と中長期プラン
新規事業開発が「しんどい」状況を脱却するには、目先の負荷を減らす短期対処と、事業を正しい方向へ導く中長期プランの両輪で進めることが重要です。
まず、なぜ短期と中長期の両方が必要なのかを理解し、次に短期的な「勝ち筋」の検証に集中します。
そして、チームの燃え尽きを防ぐ考え方を身につけましょう。
この2つの視点を組み合わせることで、チームの疲弊を防ぎながら、着実に事業を成功へ導くことができます。
なぜ短期的な負荷軽減と中長期の軌道修正が両方必要なのか
新規事業開発の「しんどい」は、短期的な問題(過剰なタスク)と中長期的な問題(事業の方向性のズレ)が絡み合って発生します。
例えば、目の前のタスクに追われて1日12時間労働が続くとチームは疲弊します(短期の問題)。
しかし、その原因が不明確な事業目標にある場合(中長期の問題)、タスクを減らすだけでは根本解決になりません。



目の前のことで手一杯なのに、長期的なことまで考える余裕がありません…



だからこそ、まず短期対処で心の余裕を作り、その上で中長期の計画を見直す順番が大切ですよ。
| 課題の種類 | 具体的な問題例 | 必要な対策 |
|---|---|---|
| 短期的な課題 | 終わらないタスク、頻繁な仕様変更 | 業務の優先順位付け、MVPの再定義 |
| 中長期的な課題 | 曖昧な事業目標、ステークホルダーとの認識齟齬 | ロードマップの簡素化、KPIの再設定 |
短期的な対処で応急処置をしつつ、中長期的な視点で根本原因を取り除くことで、持続可能な事業開発体制を築けます。
まずは「勝ち筋」の検証に集中する重要性
「勝ち筋」とは、「誰の・どんな課題を・どのように解決すれば事業が成長するか」という最も重要な仮説を指します。
多くのチームは多機能な製品開発にリソースを注ぎ込みがちですが、成功している事業は特定の顧客層とひとつの機能に絞り、仮説検証に集中しています。
例えば、メルカリは初期に「CtoCで簡単に出品できる」という1点に絞って勝ち筋を見つけました。



色々なことを試さないと、何が当たるかわからないのでは?



リソースが限られているからこそ、最も可能性の高い仮説に集中投下して、素早く答えを出すことが成功の近道です。
多くのタスクに手を出すのではなく、最も確度の高い「勝ち筋」の検証にチームのリソースを集中させることが、新規事業開発のしんどい状況を打開する鍵となります。
チームの燃え尽きを防ぐための基本的な考え方
チームの燃え尽き、いわゆる「バーンアウト」は、過度なストレスと達成感の欠如が続くことで起こる心身の疲弊状態です。
特に新規事業開発では、約7割のメンバーが半年以内に高いストレスを感じるというデータもあります。
これを防ぐには、単に労働時間を減らすだけでなく、心理的安全性の確保や小さな成功体験の積み重ねが不可欠です。
| 対策の方向性 | 具体的なアクション | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 心理的安全性の確保 | 週に1回のチェックインミーティング(KPT法など) | 課題や不安を早期に共有、孤立感の解消 |
| 小さな成功体験の創出 | 検証可能な最小単位の目標設定(週次スプリント) | モチベーションの維持、チームの一体感向上 |
| 休息の制度化 | ノーミーティングデーの設定、定期的な1on1面談 | 集中できる時間の確保、個人のコンディション把握 |
チームが最大の力を発揮するためには、意識的に心理的安全を保ち、小さな成功を共有しながら前進できる文化を築くことが重要です。
新規事業開発がしんどいと感じる主な4つの原因
新規事業開発が「しんどい」と感じる根本的な原因は、不確実性の高さと周囲の期待とのギャップにあります。
この状況は、ステークホルダーとの期待値のズレや深刻なリソース不足に加え、意思決定の遅さや検証されないまま増え続けるタスクなど、複数の問題が重なって起きています。
まずはこれらの原因を一つひとつ分解して、何がチームを最も苦しめているのかを特定することが、解決への第一歩となります。
原因①:ステークホルダーとの期待値のズレ
ステークホルダーとの期待値のズレとは、事業部長や投資家といった関係者が求める成果のスピードや事業規模のことです。
これと現場チームが現実的に達成可能と考える目標との間に、大きな差がある状態を指します。
例えば、経営層は3ヶ月での黒字化を期待している場合があります。
一方で、現場は同じ3ヶ月で顧客課題の仮説検証を目標としているケースもあります。
このように、時間軸やゴール設定に1年以上のズレが生じることも珍しくありません。



報告のたびに、話が噛み合わないのはなぜ?



期待されている「成果」の定義が、お互いに違っているからです。言葉の定義をそろえることから始めましょう。
| 確認項目 | 目的 | 確認方法の例 |
|---|---|---|
| 事業のゴール | 「成功」の定義を具体化 | 3年後の具体的なユーザー数や売上目標を数値で合意 |
| 短期的なマイルストーン | 直近3ヶ月で達成すべきことの明確化 | 「顧客獲得」ではなく「課題を持つ顧客10人へのインタビュー完了」など行動ベースで設定 |
| 報告の頻度と内容 | コミュニケーションコストの最適化 | 週次での簡単な進捗報告と、月次での詳細なレビュー会を設定 |
| 失敗の定義 | 健全な撤退基準の合意 | 「3ヶ月で顧客課題の存在を証明できなければピボット」など、事前に条件を決定 |
定期的に対話を行い、事業フェーズごとに共通の言葉と具体的な数値目標を共有することで、無用なプレッシャーが減り、チームは本質的な価値検証に集中できます。
原因②:人手や予算という深刻なリソース不足
深刻なリソース不足とは、事業計画の実行に必要な人員、予算、時間が絶対的に足りていない状態を指します。
新規事業は既存事業と比べて優先度が低く見られる傾向があり、必要な支援を得にくいという構造的な課題を抱えています。
私の経験では、担当者2名だけでマーケティングから開発、営業まで全てを兼務し、月間の活動予算がわずか10万円というケースもありました。
これでは高速な仮説検証サイクルを回すことは困難です。



人が足りないのに、やるべきことばかり増えていく…



「やらないこと」を決めるのが重要です。限られたリソースで最大効果を出すために、外部の力を借りる選択肢も持ちましょう。
| 対策の種類 | 具体的なアクション | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 業務の絞り込み | MVP(最小実用製品)の再定義 | 開発工数と検証期間の短縮 |
| 外部リソースの活用 | 業務委託や副業人材の採用 | 専門スキルを短期的に補完 |
| ツールによる自動化 | MAツールのHubSpotやSFAのSalesforceを導入 | 手作業を減らし、コア業務への集中 |
| 社内リソースの借用 | 関連部署から週1日だけ人員を借りる交渉 | 一時的な人手不足の解消 |
全てを自前でやろうとせず、外部サービスや人材、他部署の協力を積極的に活用する視点を持つことで、新規事業開発のしんどい状況を乗り越えることができます。
原因③:遅々として進まない意思決定プロセス
遅々として進まない意思決定プロセスとは、事業を前に進めるための小さな予算執行や仕様変更にさえ、多くの稟議や会議が必要になる状態を指します。
その結果、スピード感が大きく損なわれてしまいます。
例えば、5万円の広告出稿に1週間、軽微なUI変更に役員が出席する会議での承認が必要といった状況では、市場の変化に対応できません。



ちょっとしたことを決めるのにも時間がかかりすぎて、つらいです…



現場チームに一定の権限を委譲してもらう交渉が必要です。判断基準を明確に示し、信頼を得ることから始めましょう。
| 提案内容 | 目的 | 交渉相手 |
|---|---|---|
| 少額決裁権の委譲 | 10万円以下の予算執行をチームリーダーの判断で可能にする | 事業部長、経理部 |
| 定例報告会の変更 | 週次の進捗報告会を「報告」から「意思決定」の場に変える | 直属の上司、事業部長 |
| 判断基準の事前合意 | 「この指標がXを超えたら次の施策に進む」というルールを事前に合意 | ステークホルダー全員 |
| コミュニケーションツールの導入 | ChatworkやSlackでの確認を正式な承認プロセスとする | 関係部署、情報システム部 |
「どのレベルの意思決定を、誰が、いつまでに行うか」というルールを事前に設計し合意形成することで、不要な待ち時間をなくし、事業開発の速度を上げることが可能になります。
原因④:検証されないまま増え続けるタスク量
検証されないまま増え続けるタスク量とは、顧客のニーズや課題が明確でないのに、「あった方が良さそう」という発想で機能開発や調査タスクが次々と追加される状態です。
その結果、チームは本来取り組むべき価値検証から遠ざかってしまいます。
この状態に陥ると、「本当にこの機能は必要なのか?」という疑問を抱えながら作業することになり、チームのモチベーションは著しく低下します。
気づけばバックログには100以上のタスクが溜まり、何から手をつけるべきか分からなくなります。



やってもやっても仕事が終わらないし、成果にも繋がらない…



「何を検証するためのタスクなのか?」を常に問い直す習慣が大切です。仮説に基づかないタスクは、勇気を持って「やらない」と判断しましょう。
| 項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
| 解決したい顧客の課題 | 忙しいビジネスパーソンが、平日の夕食を準備する時間がない |
| 提案するソリューション | 15分で調理可能なミールキットの提供 |
| 検証したい仮説 | ユーザーは月額8,000円を支払ってでも、このサービスを利用したい |
| 検証に必要なタスク | ランディングページを作成し、事前登録者数を計測する |
| 成功の判断基準 | 1週間で100人の事前登録者を獲得する |
すべてのタスクを「どの仮説を検証するものか」という視点で見直すことが大切です。
検証に直結しない作業を一時停止することで、チームは重要な活動に集中でき、成果への手応えも得やすくなります。
しんどい状況を打破する今すぐできる5つの対処法
新規事業開発がしんどいと感じた時は、まずチームの負荷を即座に下げ、心理的な余裕を取り戻すことが最優先です。
具体的には、優先タスクの洗い出しやMVPの再定義で作業を絞り込み、外部リソースの活用で人手不足を補います。
さらに、チームの心理的安全確保で基盤を固め、ステークホルダーへの報告で認識のズレを防ぐという5つのアクションで状況を改善しましょう。
これらの対処法を1〜2週間で実行することで、チームは疲弊から回復し、事業の「勝ち筋」検証に集中できるようになります。
優先すべき5つのタスクの洗い出しとそれ以外の凍結
まずは「やること」と「やらないこと」を明確に分け、チームのエネルギーを最も重要なタスクに集中させる必要があります。
現在抱えているタスクをすべて書き出し、事業の仮説検証に直結するインパクトが大きい上位5つのタスクだけを残し、それ以外はすべて「凍結」します。



タスクが多すぎて、どれを優先すればいいか分かりません…



緊急度と重要度の2軸で評価し、仮説検証に最も貢献するものを選びましょう。
| 優先順位 | タスクの例 | 目的 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1 | ターゲット顧客5名へのインタビュー | 課題仮説の検証 | リーダー |
| 2 | 最低限の機能を持つLP作成 | 解決策への需要調査 | Aさん |
| 3 | LPへのアクセス解析設定 | データ計測の準備 | Bさん |
| 4 | 競合サービスの機能比較 | 市場での立ち位置確認 | Cさん |
| 5 | 週次進捗の報告資料作成 | ステークホルダーとの合意形成 | リーダー |
このようにタスクを絞り込むことで、チームは混乱から抜け出し、具体的な成果に向けて一直線に進むことが可能です。
1機能と1顧客層で定義する最小実用製品(MVP)
MVP(Minimum Viable Product)とは、顧客に価値を提供できる最小限の機能を持つ製品を指します。
多機能な製品を目指すのではなく、「たった1つのコア機能」を「最も課題を抱えている1つの顧客層」に提供することに絞り込み、1週間で仮説検証を完了させましょう。
| 項目 | MVPの定義例 |
|---|---|
| ターゲット顧客層 | 東京都内で働く30代の共働き女性 |
| 顧客の課題 | 平日の夕食準備に時間がかけられない |
| 提供するコア機能 | 15分で調理可能なミールキットのWeb注文機能 |
| 検証する仮説 | ターゲットは月額5,000円でこのサービスを利用するか |
| 検証方法 | Googleフォームを使った事前登録とアンケート |
MVPを小さく定義し直すことで、開発リソースを節約し、市場の反応を素早く得られます。
外部人材やツールによる短期的な問題解決
人手不足やスキル不足は、外部のリソースを活用することで短期的に解決できます。
例えば、プロ人材のマッチングサービスであるサーキュレーションやビザスクを活用すれば、特定の業務経験を持つ専門家を最短1ヶ月からプロジェクトに迎えることが可能です。



外部に頼むと、かえってコストや手間がかかりそうで不安です。



目的と期間を絞れば、正社員採用より低コストで素早く成果を出せますよ。
| 活用リソース | 解決できる課題 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| サーキュレーション | Webマーケティング戦略の立案 | 月額30万円〜 |
| クラウドワークス | LPデザインや記事コンテンツの作成 | 1案件5万円〜 |
| Slack | チーム内の迅速なコミュニケーション | 無料〜 |
| Backlog | タスクと進捗の可視化 | 月額2,640円〜 |
自社で全てを賄おうとせず、必要なスキルやツールを外部から調達することで、事業開発のスピードは格段に上がります。
チームの心理的安全性を確保する週次チェック
心理的安全性とは、チーム内で誰もが安心して意見や懸念を表明できる状態のことです。
毎週月曜の朝に15分だけ時間を確保し、匿名で回答できるGoogleフォームなどを使って、各メンバーのコンディションや課題感を把握する仕組みを導入しましょう。
| チェック項目 | 質問の例 | 目的 |
|---|---|---|
| 今週の気分 | 5段階評価で選択 | メンタル状態の把握 |
| 業務上の懸念 | 自由に記述 | 課題の早期発見 |
| チームへの要望 | 自由に記述 | 関係性の改善 |
| サポートが必要なこと | 自由に記述 | 協力体制の構築 |
この週次チェックを習慣化することで、問題が深刻化する前にリーダーが介入し、チーム全体のパフォーマンス低下を防げます。
3分で現状を伝えるステークホルダーへの報告術
ステークホルダーとの認識のズレは、定期的で簡潔な報告によって解消できます。
複雑な資料は不要です。
「現状」「課題」「次のアクション」の3点に絞り込んだ報告を、毎週金曜日の夕方など決まった時間にメールで送りましょう。



報告資料を作る時間すらなくて、後回しになりがちです…



箇条書きのテキストだけで十分です。大切なのは頻度と分かりやすさですよ。
| 報告項目 | 記述内容の例 |
|---|---|
| 現状(事実) | 今週はターゲット顧客5名にインタビューを実施し、3名が課題に強い共感を示しました |
| 課題(問題点) | 一方で、提案した解決策への支払意欲は低いというフィードバックがありました |
| 次のアクション(対策) | 来週は解決策の訴求内容を変更したLPで、事前登録数を計測します |
このシンプルな報告を続けることで、ステークホルダーからの信頼を得られ、スムーズな意思決定を引き出すことが可能になります。
事業を軌道に乗せるための中長期的な改善プラン
短期的な対処でチームの負荷を下げると同時に、事業を継続的に成長させるための土台作りが不可欠です。
中長期的な視点で重要なのは、変化に対応できる柔軟な計画と、成果を正しく測る指標を持つことです。
ここでは、ロードマップの簡素化、KPIの再設定、組織体制の見直し、そして情報共有の仕組み化という4つの改善プランを解説します。
これらのプランを実行することで、チームは目指すべき方向に迷わず進めるようになり、新規事業開発の「しんどい」状況から脱却できます。
四半期単位で見直すロードマップの簡素化
年単位で描かれた壮大なロードマップは、予測が難しい新規事業開発では形だけの計画になりやすいものです。
まずは計画の期間を四半期(3ヶ月)単位に短縮しましょう。
Apple社がiPhoneを開発した際も、初期段階では完璧な計画はなく、短いサイクルで試作品の評価と改善を繰り返したと言われています。
まずは3ヶ月で達成すべき「顧客の課題解決」を1つだけ設定するのがポイントです。



長期計画だと、途中で状況が変わって対応できない…



四半期ごとの見直しなら、市場や顧客の変化に素早く対応できますよ。
四半期ごとに目標と進捗をステークホルダーと共有することで、期待値のズレを防ぎ、現実的な計画で事業を進められるようになります。
本質的な成果に繋がる重要業績評価指標(KPI)への再設定
重要業績評価指標(KPI)とは、事業目標の達成度を測るための具体的な指標を指します。
新規事業開発の初期段階で、売上や契約数といった最終成果(KGI)に近い指標を追うのは、チームのモチベーションを削ぐ原因になります。
例えば、月額課金サービスの開発初期では、KPIを売上に置くのではなく、無料トライアル後のアンケート回答率70%や特定機能の利用ユーザー数100人といった、顧客の価値検証につながる行動指標に設定します。
| 項目 | 見直し前のKPI(例) | 見直し後のKPI(例) |
|---|---|---|
| 指標の種類 | 最終成果(遅行指標) | プロセス指標(先行指標) |
| 具体例1 | 月間売上100万円 | 課題解決を実感したユーザーの声10件 |
| 具体例2 | 新規契約数50件 | MVPの主要機能利用率30% |
| 目的 | 収益の確認 | 顧客課題と解決策の検証 |
このようにKPIを再設定することで、チームは日々の活動が事業の成功にどう繋がるかを実感でき、つらい状況でも前向きに進むことが可能になります。
意思決定を早めるための組織体制の見直し
新規事業開発の「しんどい」原因の一つに、遅々として進まない意思決定があります。
この課題を解決するには、チームリーダーに権限を委ねることが欠かせません。
Amazonでは「Two-Pizza Rule(ピザ2枚で足りる少人数チーム)」が有名です。
しかし大切なのは人数ではなく、たとえば予算が50万円以内なら上長の承認なしで実行できるといった、自律的な意思決定権を持つことです。



上司の承認待ちで、1週間もプロジェクトが止まってしまう…



チーム内で完結できる範囲を明確にすれば、スピード感は格段に上がります。
チームに裁量権を与えることで、現場は顧客や市場の変化に即座に対応できるようになり、事業の成功確率を高めることができます。
ChatworkやBacklogを活用した情報共有の仕組み化
チーム内の情報格差や認識のズレは、無駄な手戻りを生み、精神的な疲弊に繋がります。
ビジネスチャットやプロジェクト管理ツールを導入し、情報共有のルールを定めることが重要です。
例えば、日々の簡単な連絡や相談はChatworkで行い、タスクの担当者や期限はBacklogで管理するといった使い分けを徹底します。
これにより、誰が何をしているのかが一目でわかるようになります。
| ツール | 主な用途 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| Chatwork | リアルタイムなコミュニケーション、簡単な質疑応答 | 意思疎通の円滑化、会議時間の削減 |
| Backlog | タスク管理、課題の進捗追跡、ガントチャート作成 | 担当と期限の明確化、進捗の可視化 |
| Google Drive | ドキュメント共有、議事録作成、データ保管 | 情報の一元管理、属人化の防止 |
このような仕組みを整えることで、報告のための会議が減り、チームメンバーは本来取り組むべき開発や検証作業に時間を割けるようになります。
新規事業開発を成功に導くための本質
新規事業開発で「しんどい」と感じる状況を乗り越えるには、短期的な対処だけでなく、事業を継続的に成長させるための本質的な考え方が重要です。
ここでは、新規事業開発プロセスの全体像を振り返り、失敗から学んで軌道修正した成功事例を紹介します。
さらに、担当者のメンタルケアや孤立を防ぐための外部相談先についても解説します。
これらの本質を理解すれば、目の前の困難を乗り越えるだけでなく、将来にわたって持続可能な事業開発体制を築けるようになるでしょう。
新規事業開発におけるプロセスの全体像
新規事業開発のプロセスとは、アイデアの発想から市場投入、さらに事業の成長まで続く一連の流れを意味します。
このプロセスが一直線に進むことはほとんどなく、実際には「仮説構築」→「検証」→「学習」→「方向転換」というサイクルを何度も繰り返すことが、成功の鍵となります。
例えば、リーンスタートアップの考え方では、顧客からのフィードバックを元に平均して5回以上のピボット(方向転換)を行うことが一般的です。
| フェーズ | 主要な活動 | アウトプット |
|---|---|---|
| アイデア創出 | 市場調査、課題発見、ブレインストーミング | 事業アイデアのリスト |
| 価値検証 | 顧客インタビュー、MVP(最小実用製品)開発 | 検証済みの中核価値 |
| 実証実験 | PoC(概念実証)、テストマーケティング | 事業化の判断材料 |
| 事業化 | 製品開発、販売チャネル構築、マーケティング | 市場投入された製品/サービス |
| グロース | KPIモニタリング、機能改善、顧客獲得 | 持続的な事業成長 |
全体像を見渡すことで、現在の立ち位置と次に取り組むべきことが明確になり、新規事業開発の進め方における迷いを減らせます。
失敗から学ぶ軌道修正の成功事例
新規事業開発における失敗は、成功へつながる貴重な学習データとなります。
大切なのは、失敗を早期に見つけ出し、迅速に軌道修正することです。
例えば、写真共有SNSのInstagramは、当初「Burbn」という位置情報共有サービスとしてスタートしました。
しかし、ユーザーが主に写真投稿機能だけを利用していると分かり、その機能に特化して大胆に方向転換した結果、世界的なサービスへと成長しました。



うちの事業も、このまま進めていいのか不安です…



データに基づいて、顧客が本当に価値を感じている部分を見極めることが重要ですよ。思い切った方向転換がブレークスルーを生みます。
このように、新規事業の失敗原因を冷静に分析し、顧客の反応を素直に受け入れる姿勢こそが、最終的な成功につながります。
担当者に求められるメンタルケアと休息の取り方
新規事業開発は予測不能なことの連続であり、担当者には想像以上の精神的プレッシャーがかかります。
そのため、意識的なセルフケアが不可欠です。
チームリーダーとして、メンバーのバーンアウト(燃え尽き症候群)を防ぐことも重要な役割です。
例えば、Google社では業務時間の一部を自由な研究開発に使うことを許容し、創造性とモチベーションを維持しています。



チームのモチベーションが下がっていて、どうすればいいか分かりません…



まずは意識的に休息を取る時間を作りましょう。15分の散歩や、週に1度は「ノー会議デー」を設けるだけでも効果があります。
| 項目 | 具体的なアクション | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 短時間の休息 | 25分集中して5分休憩するポモドーロ・テクニックの導入 | 集中力の維持と疲労軽減 |
| 業務の区切り | 業務終了時刻を決め、PCをシャットダウンする | 仕事と私生活の切り分け |
| 心理的安全性 | 週次ミーティングで「うまくいかなかったこと」を共有する時間を作る | 失敗を許容する文化の醸成 |
| 成果の可視化 | 小さな成功(例: ユーザーからの好意的な意見)をチームで祝う | 達成感の共有と士気向上 |
チームが健全でなければ、良い事業は生まれにくくなります。
新規事業開発における意識的なメンタルケアは、長期的な成功のための大切な投資と考える必要があります。
相談先としての外部メンターやコミュニティの活用
社内だけで課題を抱え込むと視野が狭くなり、社内調整がしんどい状況に陥って行き詰まることがあります。
そんな時には、客観的な視点を与えてくれる外部の存在が大きな助けになるでしょう。
専門的な知見を持つ外部メンターや、同じような課題を抱える起業家コミュニティに参加することで、新たな解決策のヒントを得られます。
例えば、プロシェアリングサービスの「サーキュレーション」では、特定の課題に対して数ヶ月単位で専門家のアドバイスを受けることが可能です。
| サービス名 | 特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| MENTA | 個人で活動する専門家にオンラインで相談できる | 特定のスキルや技術的な課題について相談したい人 |
| NPO法人ETIC. | 社会起業家向けの支援プログラムやコミュニティを提供 | 社会課題解決型の事業に取り組んでいる人 |
| Creww | オープンイノベーションを目的とした企業とスタートアップのマッチング | 大企業のリソースを活用したいスタートアップ |
| サーキュレーション | 経験豊富なプロ人材をプロジェクト単位で活用 | 経営戦略や事業開発の壁打ち相手が欲しい人 |
孤独感は、新規事業開発の最大の敵です。
積極的に外部と繋がることで、精神的な支えを得ながら、事業を前進させる力を得ることができます。
まとめ
本記事では、立ち上げフェーズのリーダーに向けて解説しました。
新規事業開発がしんどい・つらいと感じる状況では、まず目の前の負荷を素早く軽減し、勝ち筋の検証にリソースを集中させることが最優先です。
- 期待値のズレの整理
- 上位5タスクの絞り込み
- 1機能×1顧客層のMVP定義
- 心理的安全性の確保
まずは全タスクを可視化し、優先度の高い5つに絞り込みましょう。
1機能×1顧客層のMVPを設定し、今週から週次で検証を回します。
さらに、外部リソースの活用と簡潔な週次報告を行うことで、意思決定を早める取り組みを今日から実行してみてください。