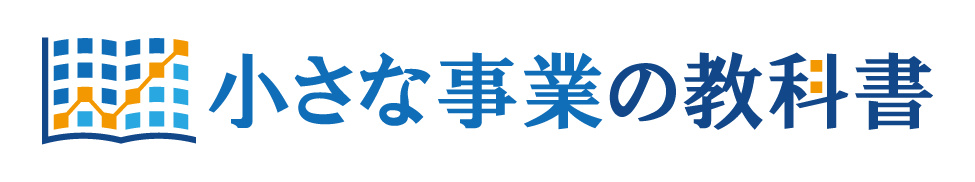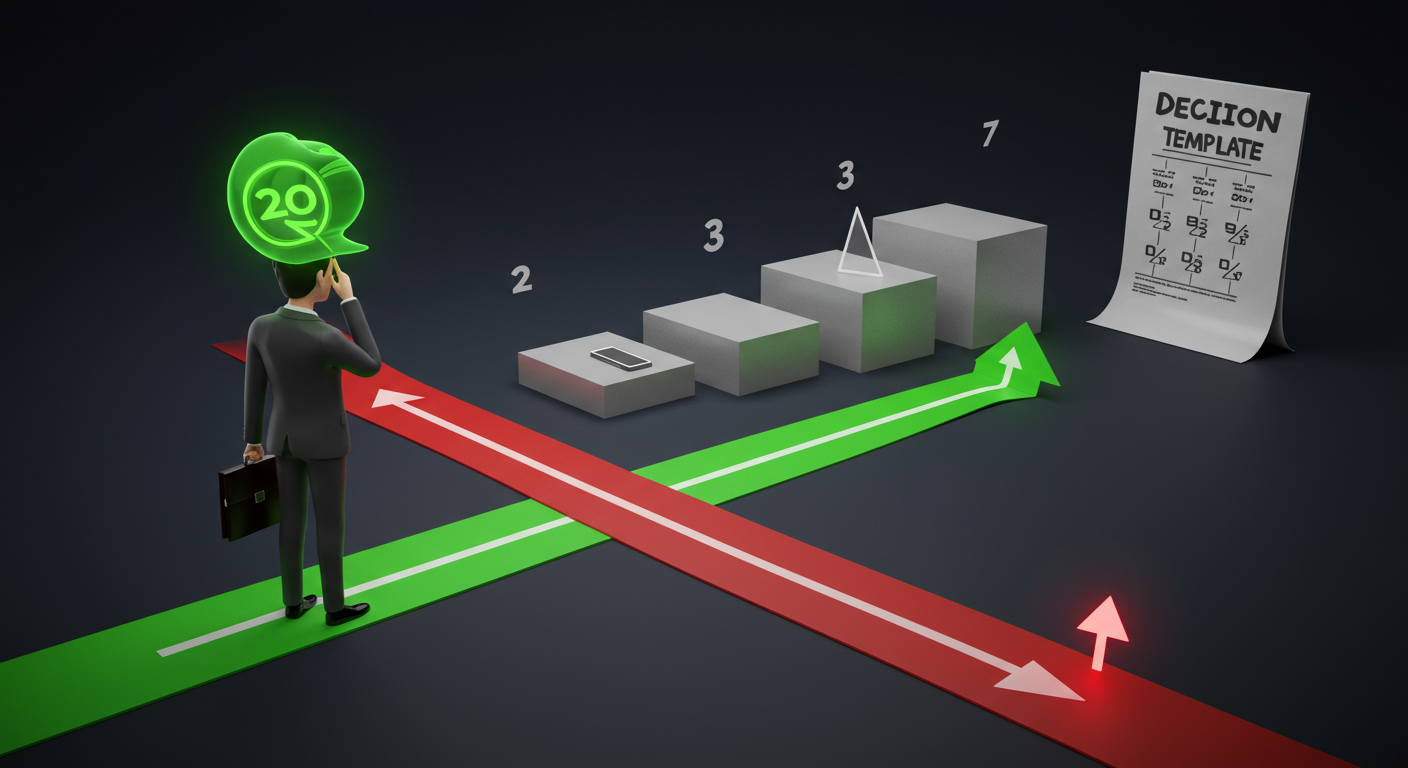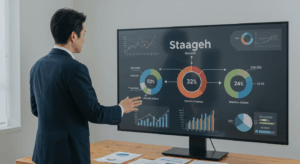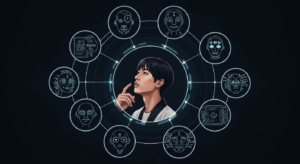新規事業を進める上で最も大切なのは、撤退の判断となる数値目標(退出トリガー)と、その結果を検証する期間をあらかじめ決めておくことです。
この記事では、「新規事業の撤退基準」を実務でどのように作るかを、KPI設計や意思決定の流れとあわせて解説します。
5つの手順と撤退基準テンプレートを使って、経営層を納得させる具体的なプロセスを紹介します。
 相談者
相談者経営層を説得できる具体的な撤退基準はどう作ればよいですか?



まずは売上目安と検証期間を退出トリガーとして先に決め、KPIと意思決定フローをテンプレートで固めます。
- 退出トリガーと検証期間の設定方法
- KPI(売上・CAC・LTV)と指標設計
- 意思決定フローと責任者定義
- 契約整理・清算を含む実行テンプレート
新規事業の撤退判断を早める数値基準と運用フロー
新規事業を進めるうえで最も重要なのは、撤退を判断するための退出トリガー(数値閾値)と検証期間をあらかじめ決めておくことです。
この項目では、新規事業の撤退基準を設定する重要性を、基準を事前に決める意味、定量的な判断のメリット、撤退の遅れによるリスク、そして早期撤退がもたらす再投資の機会という4つの視点から整理します。
そして、この考え方を検証期間やKPI設計につなげます。
90日〜180日の検証期間を設定し、財務指標と顧客指標を明確に組み合わせた運用フローを構築すれば、意思決定のスピードが上がり、損失を最小限に抑えられます。
なぜ撤退基準の事前設定が重要なのか
撤退基準の事前設定とは、退出トリガー(数値閾値)と評価期間をあらかじめ定義することを指し、基準があることで判断を早く一貫して行えます。
例えば検証期間を「90日」と定め、売上や顧客獲得数の閾値を明記すると、経営層への説明が定量的になり合意形成が速くなります。
| 指標 | 事前設定の例 |
|---|---|
| 検証期間 | 90〜180日 |
| 売上目安 | 3ヵ月連続で目標売上の60%未満 |
| 顧客獲得数 | 月間獲得数50件未満 |
| 顧客獲得コスト(CAC) | ¥50,000超で要再評価 |



限られたリソースで撤退を判断する際、どの指標を最優先にすればよいですか?



まずは退出トリガーとして「売上目安」と「検証期間」を優先し、その次にCACやLTVで精査します。
事前に定めた数値基準があれば、経営層や現場への説得力が高まり迅速な判断につながります。
感情論を排除する定量的判断のメリット
定量的判断とは、KPIや退出トリガーなどの数値をもとに意思決定を行う手法で、感情や主観を排除し、誰が見ても同じ結果を導ける再現性の高い判断を可能にします。
たとえば、売上・CAC・投資回収期間といった指標を数値化して共有すれば、関係者全員が同じ基準で議論できるようになり、合意形成までのスピードが大きく高まります。
| 定量指標 | 代表的な評価基準 |
|---|---|
| 売上基準 | 3ヵ月で目標の60%未満 |
| CAC | ¥50,000を超える場合は再評価 |
| 投資回収期間 | 目安2年以内 |



データを重視すると現場の感情的反発が出そうで不安です…



データを可視化して説明すると、感情的反発は事実に基づく議論に変わります。
定量化された撤退基準は、説明責任を果たし意思決定のブレを防ぎます。
撤退判断の遅れが引き起こす経営リスク
撤退判断の遅れは、資金の無駄遣いだけでなく、機会損失や既存事業への影響といった複合的なリスクを招きます。
ここで言う機会損失とは、投資資金や人員を有望な別プロジェクトへ振り向けられない状態を指します。
| リスク | 具体的影響 |
|---|---|
| 資金枯渇 | 新規投資余力の低下 |
| 人材疲弊 | キーパーソンのリソース逼迫 |
| 市場機会喪失 | 有望案件への再投資不可 |
| ブランド影響 | 顧客や取引先信頼の低下 |



撤退を急ぐと短期的な失望が広がりませんか?



短期的なネガティブは発生しますが、長期的な資源最適化と再投資機会確保の勝ちが大きいです。
遅延は費用を雪だるま式に増やすため、数値で引き際を決めることがリスク管理上欠かせません。
早期撤退がもたらす再投資への機会創出
早期撤退とは、退出トリガーに達した段階で速やかに資源を別領域へ再配分する判断を指し、迅速な再投資により成長性の高い取り組みにシフトできます。
検証期間を90日〜180日に設定すると、過剰な追加投資を防ぎつつ十分な検証が行えます。
| 再投資先 | 期待されるベネフィット |
|---|---|
| 新しい市場検証 | 高成長分野への資源集中 |
| 既存事業の拡大 | 安定収益源の強化 |
| 技術改良 | 次回プロジェクトの成功確度向上 |
| 人材再配置 | キー人材の成果最大化 |



早期撤退で本当に次の投資につなげられますか?



退出で得た資源を明確なKPIに基づく投資案に振り向ければ、再投資の効果は高まります。
検証期間と明確な退出トリガーを用意し、早期撤退を実行できる運用フローを構築すれば、損失を抑えて再投資による成長のチャンスを確保できます。
【テンプレート付】経営層を説得する新規事業撤退基準の作り方5ステップ
撤退判断で最も重要なのは、退出トリガーとなる「具体的な数値閾値」とその「検証期間」を先に決めることです。
以下の5つのステップ(Step1〜Step5)で、退出トリガーの設定、KPI選定、評価タイミングと責任、意思決定フロー、合意形成・コミュニケーションを順に整理します。
90日検証を基本とし、財務・顧客・成長の主要指標を運用するルールを作れば、経営層への説得と早期の再投資判断が可能になります。
Step1. 退出トリガーとなる具体的な指標設定
退出トリガーとは、撤退判断を自動的に発動する「数値の閾値」です。
最重要箇所は売上・利益・顧客指標の閾値設定で、これが撤退判断の基点になります。
具体的には、売上目安、利益基準、投資回収期間、成長率、顧客獲得数、CACなどを数値化して検証期間を決めます。
| 指標 | 閾値(例) | 評価期間 |
|---|---|---|
| 売上目安 | 3ヵ月連続で目標売上の60%未満 | 90日 |
| 利益基準 | 四半期で営業利益率0%未満 | 四半期 |
| 投資回収期間 | 目安2年未満 | 評価時点 |
| 月次成長率 | 月次+/-5%未満が6ヵ月継続 | 6ヵ月 |
| 顧客獲得数 | 月間獲得数50件未満 | 月次 |
| 顧客獲得コスト(CAC) | CAC¥50,000超は要再評価 | 月次 |



どの数値を優先的に設定すればよい?



まずは売上・利益・顧客獲得関連の3指標を優先して、90日検証ルールを設定します。
退出トリガーは定量化で判断を自動化し、感情論による先延ばしを防げます。
Step2. 成果を測る主要業績評価指標(KPI)の選定
主要業績評価指標(KPI)は、事業の成功要因を測る具体的な数値です。
KPIは、売上・CAC・LTV・チャーン率などの定量指標と、市場反応などの定性指標に分けて設定します。
測定方法は、Google Analytics 4、Salesforce、マネーフォワードクラウド会計などで自動収集し、頻度は日次・週次・月次で担当を分けます。
| KPI | 測定方法 | 目安 | 測定頻度 |
|---|---|---|---|
| 売上額 | マネーフォワードクラウド会計 | 月次目標額 | 月次 |
| CAC | Salesforceと広告費データの突合 | ¥50,000未満 | 月次 |
| LTV | 顧客購買データの累積計算 | CAC比3倍以上 | 四半期 |
| 月次成長率 | GA4と受注データの比較 | +5%以上 | 月次 |
| チャーン率 | CRMデータ | 月間5%未満 | 月次 |



どのKPIをダッシュボードに載せればよい?



まずは売上、CAC、LTV、月次成長率、チャーン率をダッシュボード化します。
KPIは測定方法と頻度を決めて運用し、数値の信頼性を担保します。
Step3. 評価タイミングと責任体制の明確化
評価タイミングとは、データ収集・レビュー・意思決定までの周期と担当者を定めることです。
週次はデータ収集担当、月次は事業開発マネージャーによるレビュー、四半期は経営会議で最終決裁と明確に役割を割り当てる点が重要です。
具体的な役割分担と、レビュー頻度を次の表で示します。
| タイミング | 担当者 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 週次 | PdM(データ担当) | 指標集計と異常検知 |
| 月次 | 事業開発マネージャー | KPIレビューと改善施策提案 |
| 四半期 | 経営会議 | 撤退・継続の最終決裁 |
| トリガー発生時 | クロスファンクション会議 | 緊急検証と議事録作成 |



誰が最終判断を下すべき?



最終判断は経営会議が行い、月次レビューで経営層へ報告します。
評価タイミングと責任を明確にすれば判断の遅延を防ぎ、迅速な撤退やピボットが可能になります。
Step4. ピボットも視野に入れた意思決定フローの構築
意思決定フローは、トリガー発生・検証会議・代替案評価・経営判断の順で進む手順です。
ピボットを選ぶ基準は、仮説検証で「改善余地があるか」「追加投資で回復見込みがあるか」を定量的に評価する点です。
フローと主要基準を以下の表に示します。
| フェーズ | 所要日数 | 判定基準 |
|---|---|---|
| トリガー検知 | 0〜3営業日 | 閾値超過の事実確認 |
| 検証会議 | 7営業日以内 | データと仮説の照合 |
| 代替案検討 | 14営業日以内 | ピボットでKPI改善見込みの提示 |
| 経営判断 | 次回定例会議 | 定量閾値による採否判断 |



ピボットと撤退のどちらを優先すべき?



ピボットは追加投資と短期改善シナリオがある場合に限定して検討します。
意思決定フローを可視化すれば、検証に要する時間と判断基準を共有でき、合意形成が速まります。
Step5. 関係者との合意形成を進めるコミュニケーション計画
コミュニケーション計画は、ステークホルダー別に通知内容とタイミングを定めることです。
主要項目は社内向け説明、取引先への通知、顧客移行計画、法務チェックのタイミングです。
関係者ごとの通知先とタイミングを表で示します。
| ステークホルダー | 主な内容 | 通知タイミング |
|---|---|---|
| 経営層 | 撤退基準と影響額 | 月次レビュー時 |
| 開発チーム | 期限と作業範囲 | トリガー発生直後 |
| 取引先 | 契約解除条件と移行案 | 法務確認後14日以内 |
| 顧客 | サービス終了と代替案 | 最終決定後30日以内 |
| 人事 | 労務対応と再配置案 | 決裁後速やか |



経営層と現場の合意を得るにはどう説明すればよい?



数値根拠と検証スケジュールを示した議事録とテンプレートで説明します。
合意形成は数値とスケジュール、影響範囲を明示することで迅速に進められます。
撤退判断で用いるべき定量・定性の評価指標一覧
新規事業における撤退基準を明確にするためには、まず退出トリガーとなる「定量指標」を先に設定しておくことが大切です。
ここでは、財務指標・成長指標・顧客指標・定性指標の4つを整理し、さらにSalesforceやマネーフォワードクラウド会計を活用した測定方法を紹介します。
これらの指標を基に、検証期間(目安:3〜6ヵ月)を設けておくことで、新規事業の撤退判断をスムーズにし、損失を最小限に抑えることができます。
財務指標:売上目安・利益基準・投資回収期間
財務指標は、事業の継続可否を直接判断する数値であり、売上、利益率、投資回収期間を明確にすることが重要です。
目安として売上が目標の60%未満で3ヵ月継続、営業利益率が四半期で0%未満、投資回収期間が目標の2年を超える場合を退出トリガーと設定します。
| 指標 | 閾値 | 測定頻度 | 判定期間 |
|---|---|---|---|
| 売上目安 | 3ヵ月連続で目標の60%未満 | 月次 | 3ヵ月 |
| 営業利益率 | 四半期で0%未満 | 四半期 | 四半期 |
| 投資回収期間 | 目安2年超 | 年次試算 | 投資期間全体 |



新規事業の損切りはどの数値を最優先すればよいの?



売上のトレンドを最重視し、利益率と投資回収期間で補強判断します。
財務指標は撤退判断の最終的根拠になり、早期に数値を追える体制が必須です。
成長指標:月次成長率の推移
成長指標は、新規事業の将来性を判断するうえで重要な基準です。
基本的には、売上やユーザー数の月次成長率を中心に分析します。
具体的には、月次成長率がプラスマイナス5%以内で6ヵ月間続く場合、成長が停滞していると判断し、ピボットまたは撤退を検討する段階といえます。
| 指標 | 閾値 | 測定方法 | 判定期間 |
|---|---|---|---|
| 月次成長率 | ±5%以内が6ヵ月継続 | 月次集計 | 6ヵ月 |
| アクティブユーザー増減率 | マンスリーで停滞・減少 | イベント計測 | 月次 |
| リテンション(30日) | 目標未達 | コホート分析 | 月次 |



月次成長率が停滞したらまず何を評価すればよい?



顧客獲得経路ごとの成長率と離脱ポイントを優先分析します。
成長指標は早期に問題を検出するため、チャネル別の月次分析を必ず組み込んでください。
顧客指標:顧客獲得コストと顧客生涯価値
顧客指標は、獲得効率と将来収益性を示すため、CAC(顧客獲得コスト)とLTV(顧客生涯価値)を必ず算出します。
目安として月間獲得数が50件未満、CACが¥50,000を超える、LTV:CAC比が1.5未満は再評価トリガーにします。
| 指標 | 閾値 | 測定方法 | 判定期間 |
|---|---|---|---|
| 月間新規顧客数 | 50件未満 | CRM集計 | 月次 |
| CAC | ¥50,000超 | マーケティング費用按分 | 月次 |
| LTV:CAC 比 | 1.5未満 | 顧客別ライフタイム試算 | 四半期 |



CACが高くてLTVが低い場合はどう判断する?



まずは顧客セグメント別のCACとLTVを分解して改善余地を確認します。
顧客指標は投資継続の妥当性を判断するため、CRMと広告費データを結合して定期的に報告してください。
定性指標:市場の反応や技術的実現性の評価
定性指標は、定量だけでは見えない市場や技術の側面を評価する尺度であり、顧客の声、パートナー協力度、技術的リスクを含みます。
評価は定期的なユーザーインタビュー実施やパートナーとの契約更新率で行い、PoCで重大な技術的不具合が検出された場合は撤退要因とします。
| 指標 | 評価方法 | 重要度 |
|---|---|---|
| 顧客満足度 | サーベイと定性インタビュー | 高 |
| パートナー継続意思 | 契約更新率の確認 | 中 |
| 技術的実現性 | PoC結果の合格判定 | 高 |



市場の反応が薄いときに優先すべき定性調査は何?



ターゲット顧客5〜10名への深掘りインタビューと競合製品比較を実施します。
定性指標は早期に仮説の誤りを検出するため、定量と併せて評価することが撤退判断の精度を上げます。
Salesforceやマネーフォワードクラウド会計を活用した指標の測定方法
Salesforceやマネーフォワード クラウド会計は、KPIの自動集計と透明性確保に有用であり、日次・週次のデータ取得を自動化することで判断速度を上げます。
具体的にはSalesforceで商談・新規顧客数・チャネル別成果をトラッキングし、マネーフォワードクラウド会計で実績売上・費用・投資回収期間を算出します。
| ツール | 主な用途 | 更新頻度 |
|---|---|---|
| Salesforce | 商談管理と新規顧客集計 | 日次自動集計 |
| マネーフォワード クラウド会計 | 売上・費用の実績把握 | 日次連携 |
| Google Analytics 4 | ウェブ行動計測と流入分析 | リアルタイム計測 |



ツール連携で手作業を減らすには何が必要?



データ項目定義の統一とAPI連携設計を最初に固めます。
ツールを活用するとKPIの可視化と運用負荷低減が両立し、撤退判断を速やかに行える体制が整います。
撤退プロセスの円滑な進め方と実務上の注意点
撤退時に最も重要なのは、ステークホルダーへの透明なコミュニケーションと法務・財務の早期整理です。
以下では、契約解除や労務対応などの法務確認、撤退コスト分析と清算手続き、製造業に特化した事例研究、実務で使えるチェックリストとテンプレートを順に解説します。
契約・労務・財務の優先順位を明確にして90日以内に主要作業を完了する運用を整備することが、混乱を最小化して再投資の意思決定を早める結論です。
契約解除や労務対応など法務上の確認事項
契約解除や労務対応では、取引契約の解約条件や違約金、機密保持契約、雇用契約の整理といった法務面のチェックが中心となります。
中でも、解除期限や手続きを明確にしておくことが最も重要です。
具体的には、契約書に記載された解除条項の確認、取引先への通知手順、従業員の雇用整理や配置転換、機密情報の管理方法などを順に確認しておく必要があります。
| 項目 | 確認・対応内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| 取引契約 | 解約条項の有無と違約金の算定、通知方法の特定 | 30日以内でリスト化 |
| 労務対応 | 雇用契約の整理解約条件、配置転換案の作成、退職金見積もり | 60〜90日で決定 |
| 機密情報・知財 | 機密保持契約の有効期間確認とデータ移管計画 | 30日以内で実行計画作成 |
| 主要仕入先・下請 | 代替供給ルートと納期調整、契約解除通知ドラフト作成 | 30〜60日で交渉開始 |
| 弁護士相談 | 契約争点と労務リスクの早期レビュー | 初期段階で依頼(7営業日以内) |



契約解除でまず何を確認すればいいの?



まず契約書の解除条項と通知期間を一覧化し、違約金とリスクを弁護士にレビューしてもらってください。
契約と労務の主要事項をリスト化して弁護士レビューを受け、90日以内に主要対応を完了することが撤退の第一歩です。
撤退コスト分析と事業清算の具体的な手続き
撤退コストとは、事業撤退に伴う現金の支出(在庫処分、設備撤去、違約金、退職金など)に、未回収の投資額(前払費用や開発費)を加えた総額を指します。
これらをもとに、短期的なキャッシュアウトフローを想定して算出することが重要です。
具体的な手順としては、まずコスト項目を洗い出し、続いて短期(30日)と中期(90日)のキャッシュフローシミュレーションを行い、最後に損益分岐点を再計算します。
| 項目 | 見積り方法 | 対応目安 |
|---|---|---|
| 在庫処分費 | 棚卸評価と販売見込みで引当計上 | 30日で売却・処分方針決定 |
| 設備撤去費 | 外注見積もり+廃棄費用見積 | 60〜90日で契約締結 |
| 違約金・補償 | 契約条項に基づく金額試算 | 30日以内で確定 |
| 人件費関連 | 退職金見積と配置転換コスト | 60〜90日で精算計画 |
| 税務・会計処理 | 開発費の損金処理、減価償却調整 | 税理士と30日で確認 |



撤退時の費用見積はどう作ればいい?



短期(30日)と中期(90日)の2シナリオでキャッシュ出納表を作り、最悪ケースの現金必要額を確定してください。
撤退判断前に必ず短中期のキャッシュシミュレーションを行い、財務部門と税理士の確認を受けて清算スケジュールを作成します。
製造業における新規事業の撤退基準事例研究
製造業では設備導入費や量産立ち上げの遅れが撤退判断に大きく影響し、設備償却・リードタイム・受注転換率を基準に置くことが一般的です。
以下は中堅製造業を想定したモデルケースで、具体的な数値トリガーを示します。
| 指標 | モデル値 | 撤退トリガー |
|---|---|---|
| 検証期間 | 90日 | 90日で評価 |
| 月間顧客獲得数 | 目標100件 | 3ヵ月連続で60件未満 |
| 顧客獲得コスト(CAC) | 目標¥30,000 | CACが¥50,000超で再評価 |
| 生産立ち上げ遅延 | 目標ライン稼働60日 | 目標の2倍超で撤退検討 |
| 設備投資回収 | 目標2年 | 見積りで3年超なら縮小検討 |



製造業での「量産化失敗」はどう判断する?



量産ラインの立ち上がりが目標期間の2倍を超え、受注確度が低い場合はピボットか撤退を優先判断してください。
このモデルでは、売上・顧客数・CAC・設備回収期間の複合トリガーで判断し、90日検証で基準未達の場合は即時代替案を検討します。
すぐに使える撤退基準の運用チェックリストとテンプレート
運用チェックリストは、退出トリガーの監視、責任者、期限、アウトプットを明確にしたテンプレートで、誰がいつ何をするかが一目で分かる形式が有効です。
以下は、社内運用で使える最低限のチェックリストとテンプレート名称の例です。
| 項目 | テンプレート名 | 担当者 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 退出トリガー一覧作成 | 退出トリガー表(Excel) | PdM | 初期90日以内 |
| 月次KPIレポート | KPIレポート(Google Data Studio) | データ担当(PdM) | 毎月5日 |
| 検証会議議事録 | 検証会議議事録テンプレ | 事業開発マネージャー | 会議翌営業日 |
| 契約整理リスト | 契約整理リスト(Word) | 法務担当 | 30日以内 |
| 清算・コスト見積 | 清算シミュレーション表(Excel) | 財務 | 30日で初回 |
| コミュニケーション文面 | ステークホルダー通知テンプレ | 広報/事業 | 要時点 |



現場で使えるテンプレートはどれから用意すればいい?



まず退出トリガー表とKPIレポートを作成し、30日以内に契約整理リストと清算シミュレーションを整備してください。
このチェックリストとテンプレートを活用し、まずは90日間の検証サイクルを運用してみましょう。
必要に応じて、Google Analytics4、Salesforce、マネーフォワードクラウド会計と連携し、KPIを自動的に収集できる仕組みを整えると効果的です。
まとめ
この記事では、「新規事業の撤退基準」の実務的な作り方を解説しました。
中でも、退出トリガー(数値閾値)と検証期間をあらかじめ設定しておくことが、最も重要なポイントです。
- 退出トリガーの明確化
- KPIと測定体制の整備
- 評価タイミングと意思決定フローの定着
- 契約整理と撤退コスト分析の実行
まずは退出トリガーの一覧表とKPIダッシュボードを作成し、90日間の検証ルールに基づいて運用を開始しましょう。
あわせて、撤退基準のテンプレートや契約整理リストも準備し、社内承認を経たうえで実行に移すことが重要です。